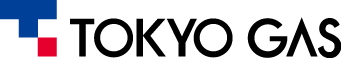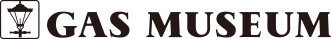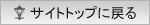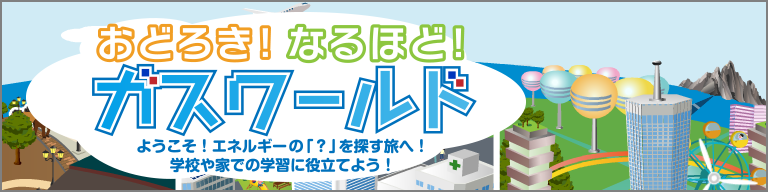企画展
~越えていく140年の炎とくらし~ 「炊飯がつなぐ日本の食文化」展
本年10月1日に、東京ガスは設立から140年を迎えます。日本で初めて灯ったガスの炎は、市中の街灯から始まり、室内灯への利用へと広がりました。電気との照明分野での競争のなか、明治30年代には調理用の熱源としての利用へと拡大していきます。

引き札 たった一本のマッチから 東京ガス(株) 明治30年代
東京ガスは、熱源利用のために当初は海外から輸入した調理器具を販売・紹介しました。しかし、輸入品は高価で使い勝手も悪く、暮らしに受け入れられにくかったことから、調理用熱源の普及はなかなか進みませんでした。
そこで当時の生活様式に受け入れやすく、手ごろな価格のガス器具の提供に東京ガスが取り組み、明治35年(1902)に開発されたのが「瓦斯竈(がすかまど)」です。広告や書籍での紹介もあり、調理用熱源としての利用は大正時代に入ると、暖房や給湯など他の用途へと広がりました。さらに昭和初期にはさまざまな国産ガス器具が登場し、都市部では熱源としてのガス利用が普及、炊飯利用が調理の重要な柱となりました。

ガスター1.2リットル炊飯器 昭和43年(1968)
戦後の昭和30年(1955)に自動式電気炊飯釜(電気炊飯器)が登場したことで、ガス自動炊飯器の開発が促され、以後炊飯分野での競争が始まりました。しかし、昭和47年(1972)にジャー機能を搭載した電気炊飯器が登場すると、炊いたご飯を長時間一台の製品で保温できる利点が受け入れられ、電気炊飯器が広く普及していきます。
一方でガス炊飯器はセンサーやマイコンをはじめとした電子部品を採用し、ガスの火力を生かした製品へと進化していきます。現在では、搭載したセンサーを活用し、コンロ上で食事ごとに炊飯を行うなど、土鍋をはじめとしたさまざまな調理器具とガスの火力を組み合わせた炊飯の利便性が紹介されています。

4升炊きガスかまど 大正時代
今回の展示では、東京ガスグループ誕生140年の歴史を振り返る中で、明治35年(1902)に誕生した「瓦斯竈(がすかまど)」から120年以上にわたり私たちの暮らしの中で活用されてきたガス炊飯の歩みを紹介し、ガスの炎と私たちの暮らしとの関わりについてお伝えします。
さらに、炊飯と日本人の生活との結びつきを紹介するため、株式会社プレナス米食文化研究所様のご協力をいただくとともに、明治5年(1872)の書籍『西洋料理指南』に西洋料理として紹介され、その後各年代を経て日本の食生活に受け入れられていった「カレーライス」の姿を、株式会社中村屋様からご提供いただいた資料とともに紹介します。これにより、各年代の雰囲気を体感していただき、炊飯とガスの炎がもたらす暮らしの豊かさについてお伝えしたいと考えています。
| 会期 | 2025年 9月27日(土) ~12月25日(木) |
| 開館時間 | 午前10時~午後5時 |
| 休館日 | 月曜日 但し、 10月13日・11月3日・24日(月・祝振休)は開館、 10月14日・11月4日・25日(火)は休館 |
| 会場 | ガスミュージアム ガス灯館2階 ギャラリー |
| 交通 | 交通情報、最寄地図はこちらをご覧ください。 |
| チラシ | 企画展チラシ |
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年